こんにちは、六角スコーンの店長(@RokkakuScone)です。
バックギャモンというゲームをご存知でしょうか?
西洋すごろくと紹介されることもありますね。
その起源はとても古く、紀元前3500年のエジプトの遺跡からその原型っぽいものが出土されています。
そのぐらい古いゲームだと長い年月を経て世界中に伝搬しており、あちこちに類似ゲームが存在します。
日本にも「盤双六」として遊ばれていた記録が日本書紀に既にあります。(ちなみに双六賭博禁止令です。)
また正倉院には、天皇家御用達の豪華な双六盤が眠っているようですね。
そんな「盤双六」ですが、江戸時代には途絶えてしまいます。
禁止令が出るほど人々が熱狂し、千年以上遊び継がれたゲームがなぜ途絶えることになったのか。
これはミステリーでしょう!

というわけで今回はこのミステリーを解き明かしたいと思います。
と言っても私は研究者ではありませんから、いろいろな人の研究や考察をご紹介するだけですけどね。
バックギャモンとは
まず、バックギャモンの詳細から。
詳しいルールはこちらのサイトを見ていただきたいのですが、ここでも簡単にご紹介します。
バックギャモンは複数の駒を使った「すごろく」です。

自分の駒をそれぞれ15個持ち、先にすべてゴールさせた方の勝ちです。
複数の駒を使いますから、それらが同じマスに止まることもありますね。
この時に自分の駒なら同じマスに重ねて置けます。
すでに相手の駒がいる場合、その駒が1つだったらそいつを蹴飛ばしてふりだしに戻してから自分の駒が入ります。
これをヒットと言います。
しかし、相手の駒が複数ある場合は自分の駒はそこに入れません。
これをブロックと言います。
ということは連続してブロックを作れば、それを越えるサイコロの目は限られてきますよね。
連続してブロックを作ることをプライムと言います。
さらに6連続プライムを作ればサイコロの目は6までしかありませんから相手はそれを越えられません。
これはフルプライムと言います。

プライムを作られると、動きが制限されてものすごく不利になります。
ましてやフルプライムなんて作られたら、動かせる駒がなくなってパスし続けなければならないことも。
これはとても悔しいですし、そんなゲームを最後まで続けたくはないですよね。
ルールではアリだがマナー違反?
ゲーム研究家で日本でただ二人の盤双六プレイヤーを自称する草場氏(もう一人は草場氏の元奥様)は、盤双六が廃れた理由としてこのプライムを挙げてます。
草場氏の説では、上流階級で「プライムはマナー違反」とされるようになり、その結果としてゲームがつまらなくなって廃れてしまったのではないか言っています。
マナー違反、つまりルールで明確に禁止されてるわけではないけど、それをすると「卑怯者」と言われるようになるわけですね。
上流階級での事ですから、身分の低い人が高い人に勝ってしまった時に「其の方の手はいささか卑怯ではないか」とか言い出したお偉いさんがいたのでしょう。
上の人が言ったことに下からは逆らえませんから、やがてその「マナー」を誰もが守るようになります。
人は誰でも一度「マナー」を受け入れてしまうと、それを守っていない人に対して「それはマナーだ」と言いたくなってしまうものです。
他にも飲み会のマナーだとか、エスカレーターで片方を空けるとか、ハンコの押し方とか、とにかく一度マナーとして定着してしまうと不合理な事でもなかなか覆せなくなりますよね。
特に敗者から勝者にモノ申せるマナーはとても広まりやすかったのではないかと思います。
コメントで別の見解を頂きました。フルプライムの禁止は確かに一部で行われていたが、江戸時代のいくつかの文献にはその記載がないことから、フルプライムが盤双六衰退の原因とは考えにくい、とのことです。
盤双六のキモ
さて、「マナー」って一つの文化(ゲーム)を絶滅させるほどの脅威なんですねってことで終わってもいいんですが、もう少し話を広げてみましょう。
プライムを作れなくなったから盤双六は衰退した説があるということは、逆に言えば盤双六のキモはプライムだったとも言えます。
一般に「双六(すごろく)」として遊ばれている、一つの駒をサイコロの目だけ動かしてゴールを目指すゲーム(絵双六)は、完全に運だけのゲームです。

そもそもゲーム中に選択肢がありませんから、上手も下手もないですよね。
大人になって同じ一本道の双六を何回も遊べと言われてもちょっとしんどいです。
一方で盤双六では、コマの進め方に選択肢があります。
プライムは作れなくてもヒットしやすい位置取りや、ヒットされにくい展開を作る楽しみもあります。
プライムにならない範囲で飛び飛びにブロックを作ることも出来るでしょう。
絵双六よりはよほど戦略的なゲームです。
それでも廃れてしまったという事は、
それでは面白さが足りなかった!
ということなんですよね。
いまの「すごろく(絵双六)」は盤双六の簡易版として始まり、盤双六から系統の分かれた、いわば妹分みたいなものです。
しかし子供向けのゲーム性のない絵双六の方が現代まで生き残り、盤双六の方は途絶えてしまった。
ゲームはなぜ廃れるのか
ここで少し話を変えましょう。
江戸時代までは碁盤・将棋盤・双六盤は「3面」と呼ばれて嫁入り道具の必需品でした。
つまり日本の伝統遊戯と言えば盤双六の他に囲碁と将棋もあります。
逆に言えば、囲碁と将棋しかありません。
他にもっといろいろな遊戯があったはずです。蹴鞠とか貝合わせとかはどこに行ったんでしょう。
様々な遊戯が生まれては流行り、そして廃れていきました。
それは何故?
ゲームとは勝ったり負けたりするから楽しいのだと思います。
TVゲームを考えてみてください。中には長く遊ばれるものもありますが、基本的に攻略されたら終わりです。
強い動きを見つけ出し、システムの裏をかき、決まったパターンを練習して習得すればだいたい勝てるようになりますね。
そうするとつまらなくなるので次の新しいゲームを探すことになります。
ゲームは勝ち方を見つけられたら(攻略されたら)衰退確定なのです。
その意味で盤双六は攻略された。
そして現代でも遊び継がれている囲碁と将棋はまだ攻略されてないということです。
Wikiでバックギャモンの歴史を見てみると、
18世紀に入るとバックギャモンはほぼ現代のものと同一のものとなっており、1753年にはエドモンド・ホイルによってルールが整理・確立された。
賭博としてのバックギャモンは18世紀末には衰退の傾向が見られ、19世紀に入ると、カードなどに取って代わられる形で賭博場では徐々に遊ばれなくなっていき、家庭などで遊ばれる純粋なテーブルゲームとなっていった。その後、ヨーロッパでは20世紀に入ると、停滞の様相を呈していた
https://ja.wikipedia.org/wiki/バックギャモンより
とあります。
盤双六が衰退した時期と似てますね。
バックギャモンも盤双六と同様に一度は攻略されたのだと思います。
バックギャモンは復活した
盤双六は衰退しましたが、バックギャモンは現在も世界中に愛好者がいます。
なぜバックギャモンは衰退しなかったのかというと、1920年代に「ダブリングキューブ」が発明されたからです。
実際「ダブリングキューブ」はものすごい発明です。
ダブルには2つの意義があり、ポイントを2倍にするという意義と、大勢が決しているゲームを終わらせるという意義がある。
特に後者について、ダブルが導入される以前は、勝敗が完全に確定するまで、優勢な側は単なる作業として、劣勢な側はわずかな逆転の望みに懸けて、ただダイスを振り続けるという実質的にほとんど意味のない行動を双方がしなければならなかった。ダブルの導入は、前述の状況を解消し、ゲームのスピーディー化をもたらしたという意味で重要であり、ダブルがこのゲームを絶滅から救ったとまで言われるほどである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/バックギャモンより
ダブリングキューブは「重要な場所にプライムを作られるなど負け確定の状態でゲームを続ける不快さ」に対する解決策にもなっています。
新しいルールによって攻略法が変わり、そして現在もまだ、絶賛攻略中というわけです。
バックギャモンも盤双六も元々は同じルールです。そして、プライムを作ることがゲームのキモであるにもかかわらず、ゲーム中盤でそれを作られると大勢が決して終盤がつまらなくなるという欠点がありました。
その解消のために、盤双六はプライムをマナー違反としましたが、それによってゲームのキモを失ってしまい、衰退しました。一方でバックギャモンは、新たなルールを作ってゲームを変えてしまうことで復活しました。
まとめ
皆さん、学校で「手遊び」ってやったことあると思います。
せーので指を上げたり下げたりして、上げた指の本数を当てる遊びなどですね。
あれは今も脈々と遊び継がれてるらしくて、うちの息子も私が教えるまでもなく学校で覚えてきました。
でも私が知ってるものより、少しルールが増えてるんですよね。
ほんの20年ばかりでも、ルールが追加されて単純なゲームがだんだん複雑に進化していく。
千年以上遊ばれたゲームも衰退するときには衰退してしまいます。それがそのゲームの持つ賞味期限なのでしょう。そして全てのゲームには賞味期限があるのかもしれません。
その賞味期限を延長する方法として、新しいルールの追加があります。バックギャモンはダブリングキューブによって復活しましたし、そうしてゲームは進化してきました。
しかし、囲碁や将棋はルールを大きく変えなくてもいまだに遊び継がれ、攻略され続けていますね。
次回はそのあたりについて書いてみたいと思います。







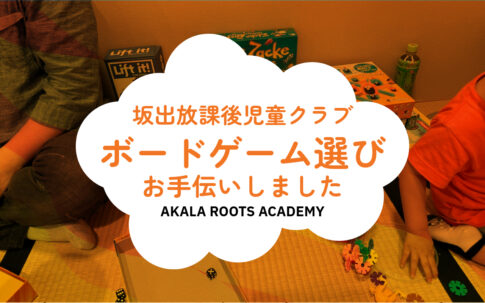



幾つか疑問に感じた記事でしたので、率直に感想を書かせていただきます。
プログラミングされたパターンで思考する前時代のテレビゲームと、人間同士でプレイする雙六を同じ次元で語られていますが、一体、雙六(盤双六)は、どのように”攻略された”というのでしょうか? 必勝法のようなものがあるのですか?
宝鏡寺や大聖寺における雙六では、フルプライム禁止のマナーがあったのは事実です。
しかし、江戸時代に出版された何冊か雙六の指南書では、いずれもフルプライムを禁止するようなことは書かれていません。むしろ現代と同じように、積極的な戦術として、ポジショニングが図面に出てきます。
1968年(昭和43年)に母親から雙六を教えられた梶浦浩二郎という方が、『雙六の遊び方』を出版され、ルールが明文化されています。ここにもフルプライム禁止とは書かれていません。
また、フルプライム禁止により雙六が衰退したという歴史的事実がわかる文献を私は見たことがありません。
これは草場純氏の妄想/想像の範疇を出ないもので、私は彼の発表した雙六に関する論文に目を通していますが、かなり杜撰な調査で、随所に間違い、勘違い、嘘を見つけました。さらに故意に歪めて書かれていることも知って、かなり悪質な印象を受けました。
宝鏡寺や大聖寺のハウスルールとして、「相手がコマを動かせなくなるようなイジワルなプレイはせず、楽しくプレイしましょう」というような趣旨のものだったとのではないでしょうか。
現代でもボードゲームをカジュアルに楽しみたい人と、ガチなトーナメントプレイで遊びたいタイプで分かれることがありますよね。
尼寺である宝鏡寺や大聖寺では、雙六遊びを継承してきた功績は大きいものがあると思います。そのことに敬意を払うことなく、歴史的事実に基づく証拠を何ら示すこともなく、まるで雙六を衰退させる要因を作ったかのような軽率な発言は、慎むべきではないでしょうか。
貴重なご意見ありがとうございます。
この投稿を作成した戎居です。
まず草場さんへの批判に関しては、私は研究者ではありませんのでどちらが正しいのかを判断する能力はありません。草場さんの説への批判があるということは了解しました。
私の文章は、草場さんの「フルプライム禁止により盤双六が衰退した」というところから出発していますので、そこが崩れたら結論もおかしなことになるかもしれません。
しかしせっかくなので、石川さんのご意見も伺いながら、改めて「ゲームはなぜ廃れるのか」を考えてみたいと思います。
石川さんは、なぜ盤双六が衰退したとお考えでしょうか?
それは端的に「飽きられた」と言ってもいいのですが、飽きたとは具体的にどういうことなのか、そこを私は深掘りしたくて本稿を書きました。
ぜひ率直なご意見を頂ければと思います。
ちなみに攻略されたというのはもちろん必勝法が見つかったということではありません。必勝法があれば、ダブリングキューブが発明されたところで復活はないですからね。
あらゆるゲームには、賭博としてプレイされていた歴史があるわけで、雙六は賭博としての魅力を徐々に失っていったように私には思えます。
四一半や七半、丁半といったサイコロ賭博の方が、瞬時に勝敗がつきますし、多人数でプレイでき、しかもいつでも参加退出が可能です。
囲碁や将棋にも金銭が賭けられ遊ばれていたわけですが、技量で勝負したい人たちにとっては、サイコロによる偶然要素の強い雙六よりも支持されたのは同然だと思います。
事実、囲碁や将棋は遊芸として、家元制度が確立されていきます。
また、戦国時代末期にポルトガルからカルタ(トランプ)がもたらされるとすぐに国産化され、全国的に流行していきます。カルタは2人だけに限らず、多人数でもプレイでき、ボードを必要としないので、手軽に遊べるところも大きいですよね。
そのためか、江戸時代の早い時期に雙六は婦女子の遊びになっています。
戯作者の柳亭種彦は「廃れし遊び雙六なり。予おさなき頃、雙六をうつ者百人に一人なり、されど下り端を知らざる童はなかりしが、近年もそれは廃れたり」と書き残しています。
彼の幼い頃というのは、寛政年間(1789〜1801年)の頃で、ここに出てくる「下り端」というのは、雙六盤の半分を使ってベアリングオフを競う簡易的な遊び方のこと、近年というのは、天保年間(1830~1844年)のことです。
江戸中期以降は、錦絵の登場でわかるように、木版多色刷りの隆盛期で、数えきれないほどの種類の絵双六が販売されています。娯楽としてのゲームは、変化に富んだ絵双六に完全に移行しています。
雙六のベアリングインしたらゲーム終了というルールは、1811年(文化8年)に出版された『雙陸獨稽古』と『雙陸錦嚢抄』に書かれているので、雙六の欠点を補うべくこの頃に考案されたルール改定であったと私は解釈しています。
1729年(享保14年)に出版された『女用智恵鑑錦織』を見ると、ベアリングオフのルールが前提となっています。
ダブリングキューブの発明が1920年代と言われていますから、日本では世界に先駆け、100年以上前にルールのテコ入れしていたことは評価すべきことで、それにより戦術性やゲーム性が損なわれたかどうかについては別問題だと捉えています。
これだけ長く遊ばれてきたゲームがなぜ衰退したのか?
ミステリアスで興味深いものがありますし、衰退要因を色々と挙げ連ねることもできるわけですが、衰退して消滅してしまったゲームは数えきれないほどあり、世代を超えて継承されるゲームの方がむしろ稀であると言えます。
現代では、デジタル・アナログ問わず、年間に何千という種類のゲームが発表されているわけですが、果たして100年後に遊ばれているゲームはどのくらいあるのでしょうか?
専門的なことは、それなりの知識を得ないことには軽率に判断できません。
だからといって、研究者でなくとも、自分なりに調べて判断することは可能だと思いますよ。
雙六の滅亡に関して、草場純氏は、
『ゲームの史的解析について』で雙六について、「このゲームは今から三百年前ほど前にほぼ滅んだ」と書いています。
https://kusabazyun.banjoyugi.net/草場純さんの研究博物館-on-web/文書/ゲーム歴史の館/ゲームの史的解析について
300年前というと、大体、1725年(享保10年)の頃のことになるのでしょうか?
『伝統ゲームを現代にプレイする意義(第5回)』では、「盤双六は、中世には猖獗を極めたにもかかわらず18世紀末にはすっかり衰退し、忘れられたゲームとなってしまう」と書いています。
https://analoggamestudies.seesaa.net/article/182789413.html
18世紀末というと、1790年代の寛政年間の頃のことになりますかね?
『盤双六』のリーフレットでは、「昭和時代にはすっかり滅亡してしまいました」と書かれています。
https://backgammon.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/Bansugoroku_web_JBL.pdf
これは、1932年(昭和7年)の杉浦三郎兵衛が雲泉荘において双六展観会を開催した直後のことなのか、それとも梶浦浩二郎が『雙六の遊び方』を出版した1968年(昭和43年)頃のことを仰っているのか? 「昭和時代」といってもかなり漠然な感じですよね。
以上、草場氏が言うことをまとめると、雙六は、江戸時代に「ほぼ」滅び、昭和時代には「すっかり」滅んだということになります(笑)。
自身の研究が進展して、アップデートすることがあるかとは思いますが、それにしても研究者としてはかなりインチキでテキトーな印象を受けました。
私は「雙六」と「バックギャモン」はルールに微妙な違いがあるとはいう、同じゲームであるという認識です。ですので、日本において現在でも滅亡はしていないと考えています。
是非、調べてみて下さい。